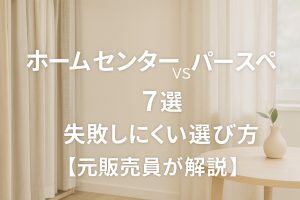一人暮らしを始めたばかりで、カーテンをドンキで揃えたあなた。
「安いし、とりあえずこれでいいか」と思って選んだカーテンが、1年後には色あせ、遮光性ゼロ、ボロボロ……そんな後悔をしていませんか?
この記事では、「ドンキ カーテン 安い」のワードで検索している方に向けて、筆者自身のリアルな失敗談とともに、遮光カーテンの落とし穴や正しい選び方を詳しく解説します。
読後には、「もう安物には手を出さない」と納得してもらえるはずです。
快適な部屋作りのために、ぜひ最後までご覧ください。
ドンキで買ったカーテンを後悔した理由5選
ドンキで買ったカーテンを後悔した理由について、実体験に基づいて詳しく解説します。
それでは順番に見ていきましょう。
①すぐに色あせてしまう
ドンキで購入したカーテンの最大の後悔ポイントは、使用して数ヶ月で色あせが目立ったことです。
特に南向きの窓に設置していた場合、紫外線によるダメージが大きく、半年後には明らかに色ムラが出てしまいました。
遮光性を期待して選んだ黒に近いグレーのカーテンも、日焼けにより赤茶けた色に変色し、部屋全体の印象が一気に古臭くなりました。
安価な染料や仕上げが原因と考えられ、UVカット加工が施されていない製品には注意が必要です。
見た目の劣化はテンションを下げるだけでなく、訪問者にも安っぽい印象を与えてしまいます。
筆者としては、最初からUVカット加工済みの遮光カーテンを選ぶべきだったと反省しています。
②遮光性がほとんどなかった
「遮光カーテン」として販売されていたにもかかわらず、朝日が差し込むと眩しくて目が覚めてしまう日々が続きました。
ラベルには「遮光率90%」と記載されていましたが、実際のところはかなり光を通してしまいます。
遮光等級は1級から3級まであり、1級は99.99%以上の遮光性を保証していますが、ドンキの格安商品は2級・3級レベルのものが多く、実用性に欠けました。
カーテンの縫製も甘く、端から光が漏れることで、部屋の暗さを保つことができませんでした。
特に夜勤明けなどで日中に眠る人には致命的な性能不足です。
光をしっかり遮りたい場合は、「1級遮光」「完全遮光」と明記されたものを選ぶことを強くおすすめします。
個人的にはニトリの1級遮光カーテンに買い替えたことで、ようやく快眠できるようになりました。
③洗濯できず不衛生になった
購入当初は気づかなかったのですが、ドンキで買ったカーテンには「洗濯不可」のタグがついていました。
ポリエステル100%でも洗える商品が多い中、なぜかこの商品は家庭での洗濯に対応しておらず、クリーニング推奨でした。
一人暮らしにとって、クリーニングに出すコストは意外と大きな負担です。
しかもホコリや花粉がつきやすい場所にあるカーテンは、定期的に洗わないと衛生的に問題があります。
実際、使い始めて1年後にはカーテンの裾が黄ばんできて、手で触るのも抵抗があるほどになってしまいました。
筆者のように「安くてラクそう」という理由で選んでしまうと、後で不衛生さに悩まされる可能性があります。
洗濯機で洗える表示があるか、購入前に必ず確認しましょう。
④布地が破れやすかった
1年ほど使用した頃、開け閉めするたびに「バリッ」という音がして、よく見ると生地に亀裂が入っていました。
特にレールと擦れる部分や、裾の折り返しなどの負荷がかかる部分から破れ始め、最終的には光が漏れるほどの大きな穴に。
触ってみると布地が薄く、引っ張るだけでも裂けそうな感触がありました。
これでは遮光性どころか、カーテンとしての役割すら果たせません。
安価なカーテンはどうしても生地が弱く、縫製も甘いため、耐久性に期待できません。
筆者としては、引っ越し初期に「とりあえず」で済ませるのではなく、ある程度の質を見極めておくべきだったと強く感じています。
⑤安っぽさが部屋全体に出た
最後に感じたのは、「部屋の印象がとにかく安っぽくなった」という点です。
カーテンは面積が広く、部屋の中で視覚的なインパクトが大きいため、素材や色がチープだと全体の雰囲気に直結します。
筆者が選んだのは光沢のあるブラウン系のカーテンでしたが、実物は写真よりも薄くてテカテカしており、まるでラッピング素材のようでした。
家具やインテリアと合わせても統一感がなく、「安く揃えた感」がどうしても漂ってしまいます。
「とりあえず感」が出ると、自分の生活空間に愛着が持てず、テンションも上がりません。
インテリアは自己表現の一部でもあるため、カーテンも安さだけで選ばず、全体の調和を意識して選ぶことが大切です。
遮光カーテンの落とし穴4つ
遮光カーテンの落とし穴について、購入前に知っておきたい注意点を解説します。
それでは詳しく見ていきましょう。
①完全遮光ではない商品も多い
遮光カーテンと聞くと、部屋を真っ暗にできるイメージを持つかもしれません。
しかし「遮光カーテン=完全遮光」ではありません。
遮光には等級があり、1級(99.99%以上の遮光性)、2級(99.80%以上)、3級(99.40%以上)と分類されています。
特にドンキやホームセンターなどで売られている安価な遮光カーテンは、2級以下のものが多く、「遮光性はあるが完全には暗くならない」レベルです。
睡眠の質を重視する人、夜勤やシフト制で日中に眠る必要がある人には不向きです。
筆者も最初は「遮光」と表示されていれば大丈夫と思い込み、結果として部屋が明るすぎて後悔しました。
「1級遮光」や「完全遮光」と明記された製品かどうか、必ず確認してください。
②光漏れが多くて眠れない
遮光性能とは別に、「光漏れ」の問題も見落とせません。
たとえ生地が高性能でも、カーテンと窓枠の隙間から光が漏れてしまえば意味がありません。
特に両開きタイプの場合、中央の合わせ目や上下左右のすき間から光が入り込むケースが多いです。
遮光カーテンを選ぶ際は、生地だけでなく設置方法やサイズ感、遮光用の工夫(カーテンボックス、サイドカバーなど)も重要です。
筆者は後からサイドカバーを導入することで改善しましたが、最初からぴったりサイズのカーテンを選べば余計な出費を抑えられたと思います。
③洗濯できない素材が多い
遮光性を高めるために、裏地に特殊コーティングを施している商品が多くあります。
しかしこの加工があると、家庭用洗濯機では洗えないものが多くなります。
とくに安価な遮光カーテンに多いのが、「水洗い不可」「ドライクリーニングのみ」といった注意書き。
一人暮らしで頻繁にクリーニングに出すのは現実的ではなく、次第にホコリや臭いが溜まりやすくなります。
衛生的にも快適性にも大きく影響するので、「洗濯機OK」の遮光カーテンを選ぶことをおすすめします。
実際、筆者はニトリの「洗える1級遮光カーテン」に買い替えて、メンテナンスのストレスがなくなりました。
④静電気でホコリがつきやすい
遮光カーテンの素材にはポリエステルが多く使用されています。
この素材は静電気を帯びやすく、空気中のホコリや花粉、ペットの毛などを吸着しやすいという欠点があります。
特に冬場や乾燥した季節は静電気がひどく、カーテンを触るたびに「パチッ」とくることもあります。
さらに、ホコリが目立つと見た目も悪く、アレルギーのある人にとっては健康への影響も懸念されます。
静電気防止スプレーや空気清浄機との併用、もしくは静電気防止加工されたカーテンを選ぶことで、ある程度は軽減できます。
筆者としては、こまめな掃除が苦手な人ほど素材に注意して選ぶべきだと感じています。
一人暮らしでありがちなカーテン選びの失敗例
一人暮らしでありがちなカーテン選びの失敗例について、体験談とともに解説します。
それでは詳しく解説していきます。
①サイズを測らず購入してしまう
一人暮らしを始めたばかりの人にありがちなのが、窓のサイズを測らずにカーテンを購入してしまう失敗です。
筆者も「多分これくらいだろう」と感覚で選んでしまい、実際に取り付けたときに長さが足りず、窓の下が丸見えになってしまいました。
また、横幅が足りず、カーテンを閉めたはずなのに光が漏れてしまうこともあります。
窓の高さと幅は、サッシ内寸ではなく「カーテンレールの端から端まで」を基準に測るのが正解です。
測る手間を惜しんだ結果、二度買いする羽目になることもあるため、購入前の採寸は必須です。
②色や柄だけで決めてしまう
カーテン売り場で一番目を引くのは「見た目」です。
そのため、「かわいい柄」や「映える色」に惹かれて購入してしまう人も多いのではないでしょうか。
筆者もパステルピンクのカーテンを衝動買いしたのですが、部屋の家具や床の色と全く合わず、結果的に浮いてしまいました。
また、実際の部屋で見ると想像以上に派手に感じて、落ち着かない空間になってしまったのです。
カーテンは部屋の印象を左右する重要な要素なので、他のインテリアとのバランスを考えて選ぶ必要があります。
インテリアが苦手な人ほど、無地やベーシックカラーを選んでおくのが無難です。
③安さだけを重視して選んでしまう
「一人暮らしはお金がかかるから、できるだけ安く済ませたい」という心理はよくわかります。
筆者もその気持ちで、ドンキの2枚組1,000円カーテンを選びましたが、数か月で遮光性も失い、布地もほつれてきました。
結局、買い直すことになり、トータルで高くつく結果に。
カーテンは1日の中で長時間目にするアイテムなので、快適さや耐久性を犠牲にすると生活全体の満足度が下がります。
「安物買いの銭失い」にならないよう、ある程度の質を持った製品を選ぶことをおすすめします。
④素材や機能性を見落としていた
見た目や価格に目を奪われて、素材や機能性を確認せずに購入してしまうのもよくある失敗です。
例えば、遮光性・防音性・断熱性・防炎性など、実は生活を快適にする大事なポイントがカーテンにはたくさんあります。
筆者は遮光性だけを重視して購入したものの、断熱性がほとんどなく、冬場は窓際がとても寒く感じました。
素材によってはホコリがつきやすいものや、静電気が起きやすいものもあります。
特にアレルギーがある人やペットを飼っている人にとっては、素材選びが重要になります。
購入前に商品説明やレビューをしっかりチェックし、自分の生活スタイルに合った機能が備わっているか確認しましょう。
買い替えるなら?おすすめのカーテンの選び方
買い替えるならどんなカーテンを選べば失敗しないのか、ポイントを整理して解説します。
それではひとつずつ見ていきましょう。
①洗えるかどうかは必須条件
一人暮らしの部屋はワンルームや1Kが多く、キッチンや窓が近い場合もあります。
そのため、油やホコリ、タバコの煙などがカーテンに付きやすく、定期的な洗濯が必要です。
購入時に「洗濯機OK」「ネットに入れて洗える」などの表示がある商品を選ぶと、手間がぐっと減ります。
筆者は以前、洗えないカーテンをクリーニングに出して数千円かかってしまい、非常に後悔しました。
カーテンは生活空間を守るフィルターのような役割もあるため、衛生的に保つことが快適な暮らしにつながります。
②遮光・断熱機能を要チェック
一人暮らしの部屋は日当たりや気温変化が大きいこともあります。
遮光カーテンであれば、1級もしくは完全遮光と明記されたものを選ぶことで、朝日や街灯の光をしっかりブロックできます。
また、断熱機能のあるカーテンは、夏の暑さや冬の冷気を遮り、エアコンの効率を上げる役割も果たします。
この機能があるだけで、冷暖房費の節約にもなり、長い目で見て経済的です。
遮光・断熱・UVカットがセットになっている商品も多く、複数の効果を持ったカーテンを選ぶと一石三鳥です。
③口コミとレビューを見て選ぶ
実際のユーザーの声はとても参考になります。
特に「1年使ってどうだったか」「洗濯後どうなったか」など、長期的なレビューは信頼性が高いです。
公式サイトだけでなく、楽天市場やAmazon、SNSで「#カーテン買ってよかった」などのタグで調べるのもおすすめです。
筆者もレビューで「ほこりがつきやすい」と書かれていた製品を避けたことで、後のストレスを減らせました。
ブランドにこだわる必要はありませんが、実際に使った人の率直な声を拾う姿勢は大事です。
④ニトリや無印もコスパ良し
実店舗で確認できて、しかも価格と品質のバランスが良いのがニトリや無印良品です。
ニトリでは「遮光1級」「洗える」「防炎」など、機能性の高いカーテンが数千円から手に入ります。
無印良品はナチュラルなデザインと素材に定評があり、インテリア全体と調和しやすいのが特徴です。
実際に生地の質感や厚みを店頭で触れるので、ネット購入に不安がある方にはぴったりです。
また、丈直しサービスなどもあるため、「サイズが合わなかったらどうしよう」という不安も解消されます。
筆者としても、最初からこれらの定番店で揃えていれば、無駄な買い替えをしなくて済んだと痛感しています。
カーテンは「安さ」より「長持ち」で選ぶべき理由
カーテンは「安さ」よりも「長持ち」で選ぶべき理由について、具体的に解説していきます。
それでは一つずつ詳しく見ていきましょう。
①長期的に見るとコスパが良くなる
カーテンは一度購入すると、少なくとも数年は使い続けるアイテムです。
仮に1,000円の安いカーテンを1年で買い替えると、5年で5,000円かかります。
一方で、5,000円で買ったしっかりしたカーテンを5年使えれば、年あたりのコストは1,000円で同じになります。
しかも後者の方が遮光性、断熱性、耐久性など、生活の質を大きく向上させてくれます。
コストだけを見ると安い方が魅力的に映りますが、「コスパ=コストパフォーマンス」を考えると、長く使える品質重視の選択が賢明です。
②住環境の快適さが大きく変わる
カーテンは単なる「窓の目隠し」ではなく、住環境の快適さに大きく影響する存在です。
遮光性が低ければ睡眠の質が下がり、断熱性が低ければ冷暖房の効きが悪くなります。
また、防音性があるカーテンであれば、騒音トラブルを軽減できる場合もあります。
カーテンひとつで室内の温度・音・光・空気感が変わるということを考えると、長持ちで高機能なものを選ぶ価値は非常に大きいです。
快適な暮らしを長く維持するためにも、カーテンの機能性にはしっかり目を向けてください。
③見た目の印象で部屋が変わる
カーテンは部屋の中でも大きな面積を占めるインテリアです。
そのため、カーテンの素材・色・質感が部屋全体の雰囲気を左右します。
安っぽいテカリのある生地や、色ムラがあるものを選ぶと、部屋全体が「安っぽい印象」になってしまいます。
一方、落ち着いた色味や上質な布地のカーテンを選べば、それだけで空間が洗練された印象に変わります。
インテリアを整えたいなら、まずカーテンにこだわるのは非常に効果的な一手です。
④安物買いの銭失いになりやすい
「とりあえず安いのでいいや」と選んだカーテンが、結果として無駄な出費になることは少なくありません。
生地がすぐに破れたり、遮光性がなくて結局別のものを買い足したりすると、二重のコストがかかってしまいます。
筆者も、最初にドンキで買ったカーテンが半年で色あせてしまい、後悔して買い替えるはめになりました。
このように、「とりあえず」で済ませた結果、二度手間・三度手間になるケースが多いのです。
カーテン選びは、値段だけでなく、使用年数・機能・満足度を総合的に見て決めるべきです。
まとめ|カーテンは安さより長持ちと機能性を重視して選ぼう
| 後悔したポイント5選 |
|---|
| すぐに色あせてしまう |
| 遮光性がほとんどなかった |
| 洗濯できず不衛生になった |
| 布地が破れやすかった |
| 安っぽさが部屋全体に出た |
一人暮らしを始めたばかりの頃は、「とにかく安く揃えたい」と思うのは当然の心理です。
しかし、カーテンは見た目だけでなく、遮光・断熱・洗濯可能かどうかなど、日常生活の質に大きく影響する重要なアイテムです。
安いカーテンを選んで後悔した筆者のようにならないためにも、少しでも「長持ち」「快適さ」に投資することをおすすめします。
快眠・節電・インテリア性を満たすカーテンは、毎日の暮らしを一段と快適にしてくれるはずです。
しっかりとレビューを読み、信頼できる商品を選びましょう。
参考になる情報として、以下の公式サイト・公的機関からも詳しいカーテンの選び方が紹介されています: