「ダイソーの室外機カバーって、本当に電気代が安くなるの?」
夏の電気代が高くなる季節、少しでも節約したいと思っている方に向けて、今回は100円ショップで手に入る室外機カバーの効果と注意点を徹底解説します。
一部では最大27%の節電効果があるとされる一方、誤った使い方で電気代が上がってしまうリスクも…。
さらに、室外機カバー以外にできる、より効果的な電気代対策についてもご紹介します。
この記事を読めば、ムダな出費を抑えながら快適な夏を過ごすための具体的な方法がわかります。
ぜひ最後までチェックしてみてください。
💡 電気代をしっかり下げたい方へ 「室外機カバー」以外にも、室温を下げる根本対策があります。
【カーテン通販どこがいい?】元販売員が選んだ遮熱・断熱に強いおすすめ5社はこちらダイソーの室外機カバーで電気代は本当に下がるのか?

ダイソーの室外機カバーで電気代は本当に下がるのか?について詳しく解説します。
①最大27%節電とされる理由

一部のエアコン室外機カバーには、「最大27%の電気代削減効果がある」と謳われている商品があります。直射日光が室外機に当たると本体温度が上昇し、冷媒の効率が下がってしまいます。遮熱カバーをつけることで熱の影響を抑え、冷房効率を維持しやすくなる仕組みです。
②5〜10%の削減は現実的?
27%削減という数値は理想的な条件下での話であり、一般家庭では5〜10%の節電が現実的です。素材や設置環境に左右されるため、万人に同じ効果があるわけではありません。
③設置条件によって効果が変わる
周囲が壁に囲まれていたり、風通しの悪い場所に室外機がある場合、カバーによって放熱効率が下がることもあります。設置環境の確認は重要です。
④SNSや口コミでの実体験まとめ
「電気代が下がった」という声もあれば、「逆に熱がこもった」という声も。効果には個人差があるため、口コミは参考程度に見るのが賢明です。
ダイソーの室外機カバーのメリット・デメリット一覧

| メリット | デメリット |
|---|---|
| ✅ 直射日光を遮り、室外機の温度上昇を防げる | ❌ 通気性を損なうと、放熱ができず逆効果になる可能性 |
| ✅ 電気代が5〜10%程度下がるケースもあり得る | ❌ 設置方法によってはエアコンの故障リスクが高まる |
| ✅ 300円以下で導入できるコスパの良さ | ❌ メーカー保証の対象外になることもある |
| ✅ 日陰がない場所では有効な遮熱手段になる | ❌ 耐久性が低く、毎年の交換が必要になる可能性 |
| ✅ DIYや応急的な対策として手軽に使える | ❌ 完全に覆ってしまうと、かえって電気代が上がる危険も |
結論:遮熱効果はあるが、「設置環境」「耐久性」「放熱確保」には十分注意が必要です。
室外機カバーのタイプ別おすすめ3選
「用途や設置環境にあわせて選べる人気の室外機カバーを3タイプご紹介します。 どれもAmazon・楽天・Yahoo!ショッピングで比較できるので、ご自宅の状況に合うものを探してみてください。」 1.アルミパネルタイプ(定番・万能) おすすめポイント: 遮熱効果が高く、シンプルで設置しやすい 直射日光から室外機をしっかり守る パンくん
パンくん3タイプ比較できるので、ご自宅の室外機に合うものを選びましょう!人気商品は在庫切れも多いので、早めのチェックがおすすめです。
室外機カバーに潜むリスクとは?
室外機カバーに潜むリスクについて解説します。
①放熱妨害でかえって電気代が上がる?
室外機カバーは、直射日光を遮る反面、放熱の妨げになる危険性もあります。
エアコンの室外機は冷媒を冷やすために大量の熱を外に逃がす構造です。
カバーによってこの放熱が妨げられると、冷却効率が低下し、かえって電力消費が増えてしまいます。


通気性のない素材や全面を覆う設計の製品には注意が必要です。
特に背面や左右の放熱フィンを覆ってしまうと、熱がこもって故障の原因にもなりかねません。
②メーカー保証の対象外になる恐れ
多くの家電メーカーでは、改造や不適切な使用による故障は保証対象外と明記しています。
そのため、純正品でないカバーを使用した結果、故障が生じた場合は修理費用が自己負担になる可能性があります。
特にカバーを取り付けた状態での温度異常やエラーが発生した場合、メーカーは責任を負いません。
このようなリスクを回避するには、正規のオプション品や、通気を確保できる設置方法を選ぶことが重要です。
③高温状態でエアコン本体への負担増
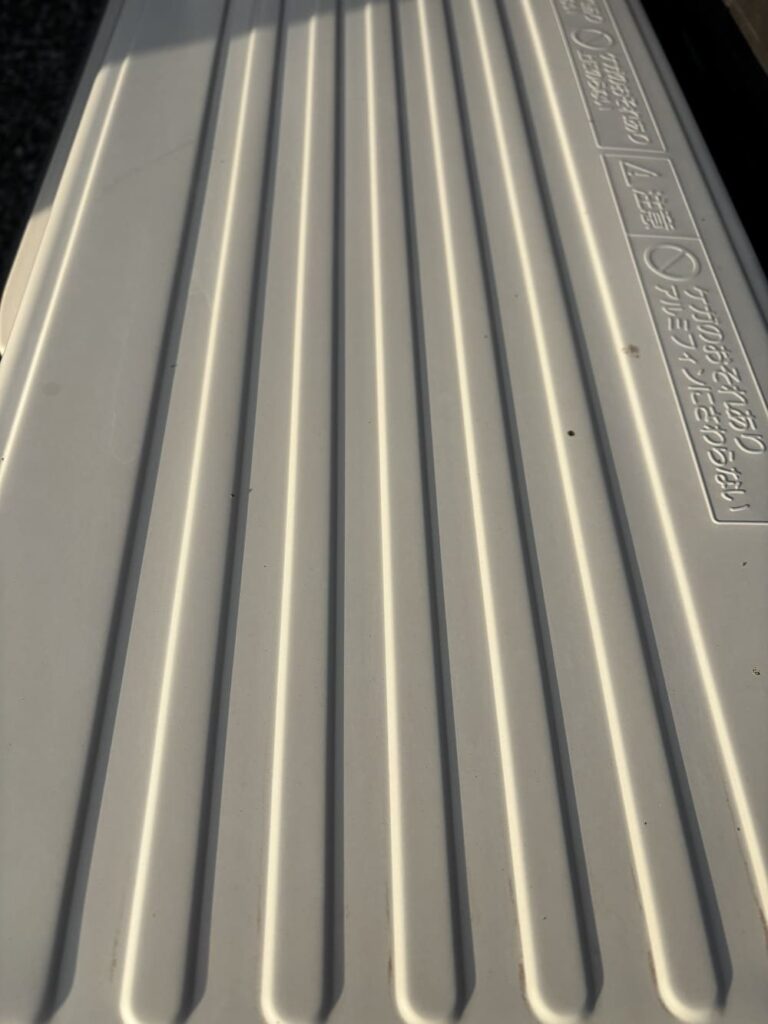
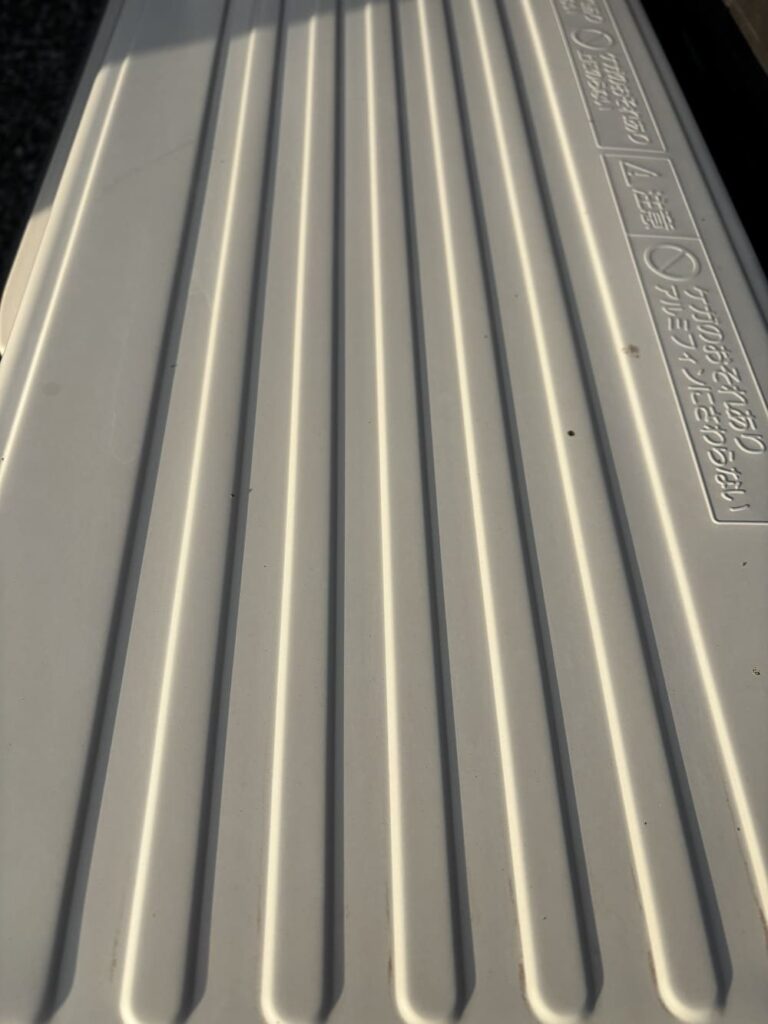
室外機の温度が上昇すると、エアコン全体の冷却効率が低下します。
その結果、室内機も余計に動作し続けなければならず、モーターやコンプレッサーに大きな負担がかかります。
この状態が長期間続くと、寿命を縮めたり、突然の故障につながる可能性も否定できません。
長い目で見ると、電気代以上に修理代や買い替え費用がかかってしまうかもしれません。
熱対策は、全体のバランスを考えたうえで行うべきです。
④長期的に見るとコスパが悪い?
室外機カバーは短期的には安価で便利ですが、長期的に見ると「耐久性」「節電効果の安定性」などで他の対策より劣るケースもあります。
| 比較項目 | ダイソー室外機カバー | 専用メーカー製カバー | 室内側の断熱対策(遮熱カーテン等) |
|---|---|---|---|
| 初期コスト | 約300円〜 | 約3,000〜10,000円 | 約2,000〜5,000円 |
| 節電効果 | 最大5〜10%(条件により低下) | 10〜20%(構造により高い) | 15〜30%(部屋全体に効果) |
| 耐久性 | 数ヶ月〜1年(劣化しやすい) | 2〜5年(屋外向け設計) | 3〜5年(屋内使用で長持ち) |
| 5年間のコスト総額 | 300円×5=1,500円+効果不安定 | 初期5,000円前後で効果安定 | 初期4,000円前後で効果安定 |
| コスパ総合評価 | ★☆☆☆☆(手軽だが限定的) | ★★★☆☆(長期使用向け) | ★★★★☆(最も安定して効果) |
このように、短期的にはコスパが良さそうに見えるダイソー製でも、5年単位で見ると専用品や室内断熱対策のほうが節電効果や耐久性に優れ、結果としてコスパも高くなることが多いです。
仮に300円のカバーで月に100円の節電ができたとしても、費用対効果としては3ヶ月で元が取れます。
しかし、通気性の悪化や本体への負担を考慮すると、そのメリットは不安定です。
また、耐久性が低い製品では、毎年買い替えが必要となることもあります。
結果的に、「節電のつもりが出費がかさむ」という本末転倒な状況に陥ることもあるのです。
節約効果とリスクを天秤にかけて、慎重に判断しましょう。
夏の電気代対策として有効な代替手段3選
夏の電気代対策として有効な代替手段3選を紹介します。
①遮熱カーテンで日差しをカット
遮熱カーテンは、外からの太陽光や熱を反射・遮断する特殊素材で作られたカーテンです。
通常のカーテンに比べて、日射熱を30〜60%カットする性能があり、冷房の効きを保ちやすくなります。
とくに西日が強く差し込む窓や、日当たりの良い部屋では効果が顕著に現れます。
ホームセンターや100均でも購入でき、取付も既存のカーテンレールで対応可能です。
電気代の削減はもちろん、室内温度の上昇を防いで体感温度を下げることにもつながります。
\レビュー評価も高めで安心!/
室外機カバー以外にも、遮熱カーテンや断熱シートは夏の節電グッズとして大人気。Amazon・楽天・Yahoo!で「遮熱カーテン」「断熱シート」と検索して比較してみてください!
②断熱シート・窓の断熱フィルムを活用


断熱シートや窓フィルムは、貼るだけで熱の出入りを抑えるお手軽な断熱アイテムです。
窓ガラスに直接貼ることで、日射熱を約30%前後カットし、冷房効率を高めることができます。
また、紫外線をカットする効果もあるため、家具や床の日焼け防止にも有効です。
手軽に導入できる反面、フィルムの質や施工の精度によって性能に差が出やすいのが注意点です。
なるべく可視光透過率が高く、遮熱性能の明示された商品を選ぶのがポイントです。
他にも手軽な節電アイテムは?断熱シートタイプの省エネカーテンライナーもおすすめ。
\価格見てびっくり。速ポチしました笑/
③間仕切りや家具配置で冷房効率アップ
空間が広すぎると冷房効率が下がり、エアコンの稼働時間も長くなってしまいます。
そのため、カーテンやパーテーションで部屋を仕切ることで冷房範囲を最小限に絞る工夫が有効です。
特にLDKのような一体化した空間では、キッチンや玄関側をカーテンで区切るだけでも冷気の漏れを防げます。
また、ソファや棚などの大型家具を空間の仕切りに活用するのも良い方法です。
冷房効率が上がるだけでなく、室内の動線を整理して快適な空間づくりにもつながります。
\今だけセール中!お得にゲット/
ダイソーの室外機カバーはこんな人におすすめ
ダイソーの室外機カバーはこんな人におすすめです。
①エアコン設置環境が日陰である


室外機がもともと日陰に設置されている場合、直射日光対策が目的となります。
そのような環境下では、通気性を損なわずに上部だけを覆うカバーの使用が有効です。
周囲の風通しが良好で、遮光のみを目的としたケースにおいては、ダイソーのカバーはコスパも良く使いやすい選択肢です。
ただし、遮光以外の断熱目的では過信しないようにしましょう。
②室外機の上部にだけ日よけしたい
エアコンの室外機の中でも特に直射日光を受けやすいのが上面部分です。
この部分だけをピンポイントでカバーしたい場合、アルミ反射素材の簡易カバーが有効です。
ダイソーの200〜300円商品の中には、ベルトで取り付けできるパネルタイプもあり、上面だけの遮熱対策として適しています。
全面を覆わないことで、放熱性をある程度確保しつつ日差しを和らげることができます。
③短期間の応急処置として使いたい


真夏の猛暑日だけ使いたい、または一時的な対策として用いたいという場合にも、ダイソー製品はコストパフォーマンスに優れています。
耐久性に難はありますが、300円以下で導入できるため、使い捨て感覚で使用するのも一つの選択です。
長期利用や強風環境には向きませんが、使い方次第では十分に役立ちます。
④DIYで状況に合わせてカスタマイズできる
ダイソーの製品は加工しやすく、DIYとの相性が良好です。
たとえば、通気性を考慮した穴あけ加工や、断熱シートとの併用など、状況に応じた工夫が可能です。
完全な既製品に頼らず、自宅の環境に合った遮熱対策をしたい方にはぴったりです。
迷ったらコレ!買う前にチェックすべきポイント
迷ったらコレ!買う前にチェックすべきポイントを整理します。
①室外機の設置場所と直射日光の関係
まずは、室外機の設置場所がどの程度日光に晒されるかを確認することが重要です。
北向きや軒下など、もともと日影の環境であればカバーの効果は限定的です。
逆に南向きや西向きで、午後の強い日差しが直撃する場所であれば、遮光効果が期待できます。
②カバーの素材と遮熱効果
カバーの素材によって、遮熱性能は大きく異なります。
アルミ蒸着シートや反射素材が使用されている製品の方が、より高い効果が見込めます。
一方、布製のものやデザイン重視の製品は、熱遮断性能が弱くなる傾向があります。
③設置方法と通気性の確保
設置時に大切なのは、室外機の「放熱経路」をふさがないことです。
上部だけを覆い、背面や側面の排熱口をしっかり確保することで、エアコン本体への負荷を防げます。
④製品レビューや評価を事前に確認
ネット通販サイトやSNSでの口コミは、製品選びの参考になります。
「遮熱効果を感じた」「通気性が悪くなった」などの意見をチェックすることで、購入後の失敗を防げます。
本気で電気代を節約したいなら見直すべき習慣
本気で電気代を節約したいなら見直すべき習慣について解説します。
それでは、それぞれの習慣について詳しく解説していきます。
①設定温度と風量の見直し


エアコンの設定温度は、電気代に直結する重要なポイントです。
環境省のデータによれば、冷房時の室温は28℃が推奨されており、設定温度を1℃上げるごとに約10%の電力を削減できます。
また、風量を「自動」に設定することで、効率的な冷却が可能になります。
一方で「弱風」にすると風の循環が悪くなり、冷房効率が落ちて逆に電力消費が増えることも。
冷気は下にたまりやすいため、サーキュレーターなどで空気を撹拌することも効果的です。
快適さと節約を両立するには、温度・風量設定をこまめに見直しましょう。
②フィルター掃除で効率アップ


フィルターにホコリがたまると、空気の流れが悪くなり冷却効率が下がります。
これにより、コンプレッサーの負荷が増え、消費電力が上がってしまうのです。
一般的に、2週間に1度程度の頻度でフィルター掃除を行うのが理想とされています。
フィルターの掃除は水洗いや掃除機で吸い取るだけでも十分効果があります。
これだけで冷房の効きが改善され、5〜15%程度の節電効果が見込めるという報告もあります。
また、内部清掃が難しい場合は業者にエアコンクリーニングを依頼するのも選択肢です。
定期的なフィルター清掃が、もっとも費用対効果の高い節電対策の一つですね。
③室内の空気循環を意識する
エアコンの冷気は部屋の下部にたまりやすく、空気が循環しないと温度ムラが生じます。
この状態では、部屋が十分に冷えないと判断され、エアコンが無駄に稼働し続けてしまいます。
そこで有効なのが、サーキュレーターや扇風機を併用して空気を循環させる方法です。
特にサーキュレーターは、天井方向へ風を送ることで部屋全体の空気を撹拌しやすくなります。
空気の流れを整えることで、設定温度を1〜2度高くしても十分な涼しさを得られるようになります。
結果的に冷房効率が高まり、電気代の節約につながるのです。
④「節電モード」は本当に節約できるか検証
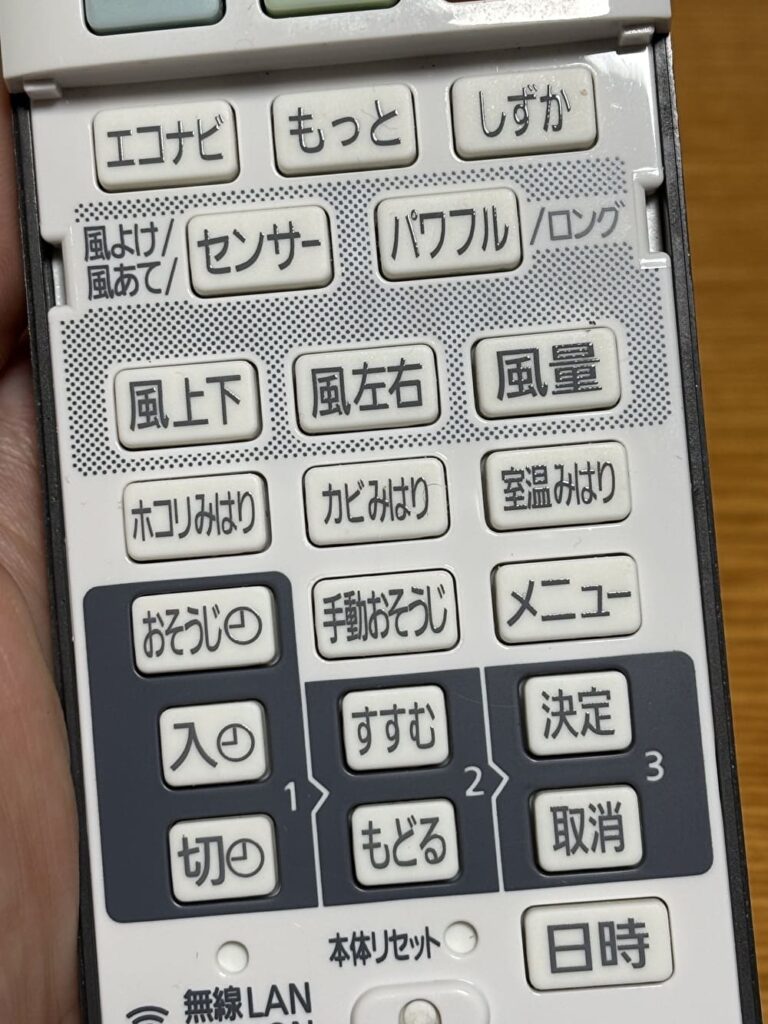
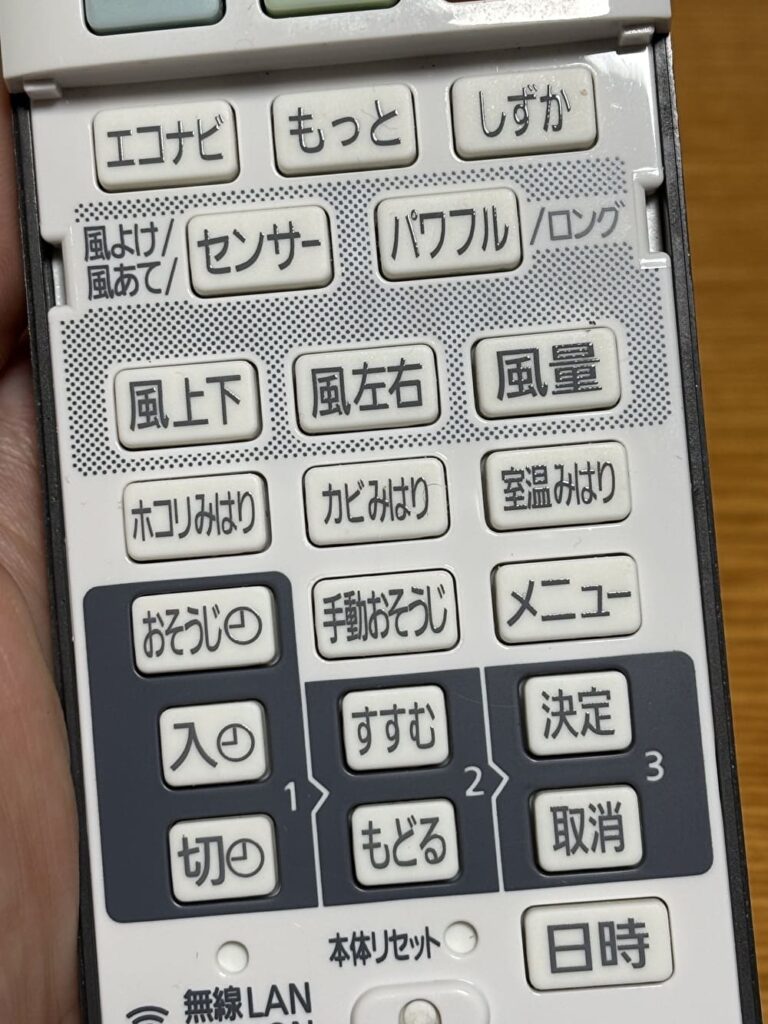
多くのエアコンには「節電モード」や「エコ運転」機能が搭載されています。
このモードを使うと、温度や風量を自動的に制御して電力消費を抑えることができます。
しかし、機種によって制御内容が異なり、冷房の効きが悪く感じる場合もあるため注意が必要です。
エコモードが実際に節電につながるかどうかは、部屋の断熱性能や使用環境にも左右されます。
過信せず、快適性と節電効果を両立させるには、必要に応じて手動での調整も組み合わせるとよいでしょう。
筆者としては、「節電モード」は補助的に活用し、基本は温度と風量の見直しで節電を図る方が確実だと考えます。
夏の電気代対策は、室内側の断熱対策も検討すべき。
夏の電気代対策は、室内側の断熱対策も検討すべきです。
- ①窓からの熱流入を遮断する重要性
- ②遮熱・断熱フィルムの選び方(換気的に出来るが効果が少ない)
- ③複層ガラス・内窓の導入効果(リフォーム費用が高いことを伝える)
- ④断熱カーテンと通常カーテンの違い
- ⑤断熱カーテンの導入効果
- ⑥カーテンで間仕切りの検討
それでは、それぞれの断熱対策について詳しく解説します。
①窓からの熱流入を遮断する重要性


夏場の室内が暑くなる主な原因は、窓からの太陽熱の流入です。
環境省によれば、住宅における熱の流入量のうち、約70%が窓からとされています。
つまり、いくらエアコンを効率よく動かしても、窓から熱が入ってきてしまえば冷房効果が打ち消されてしまいます。
このため、冷房費を節約するうえでは、まず窓の断熱性能を向上させることが最も重要なのです。
太陽光の直射を遮るだけで、エアコンの消費電力を10〜20%削減できるという試算もあります。
窓からの熱対策は、費用対効果の高い節電対策の第一歩です。
しっかりとした日差し対策を行いましょう。
②遮熱・断熱フィルムの選び方
遮熱フィルムや断熱フィルムは、手軽に貼るだけで窓からの熱の侵入を抑えられるグッズとして人気があります。
1000円〜3000円程度の製品が多く、ホームセンターやネットショップで入手できます。
ただし、断熱性能としては限定的であり、特に安価な製品では紫外線カットが主目的となっている場合もあります。
また、通気性を確保しながら断熱することは難しく、密閉状態になるため結露が発生しやすいのもデメリットです。
換気をしながら遮熱を行いたい場合は、フィルムよりもブラインドやカーテンの併用が効果的です。
筆者としては、遮熱・断熱フィルムは「補助的な対策」として位置づけ、他の断熱方法と組み合わせることをおすすめします。
③複層ガラス・内窓の導入効果(リフォーム費用が高いことを伝える)
複層ガラス(ペアガラス)や内窓(二重窓)の導入は、窓の断熱性能を大幅に向上させる最も効果的な方法の一つです。
室温の安定化、エアコンの稼働時間削減、防音効果も期待できるため、総合的な快適性が向上します。
一方で、コストが高く、1窓あたりの工事費は数万円〜十数万円に及ぶことも少なくありません。
国や自治体の補助金制度を活用すれば導入ハードルは下がりますが、賃貸住宅などではそもそも導入が難しいケースもあります。
本格的な断熱を検討している持ち家ユーザーには有効ですが、まずは低コストな対策から始めることが現実的です。
状況と予算に応じた選択が求められますね。
④断熱カーテンと通常カーテンの違い
断熱カーテンは、通常のカーテンに比べて厚手で、特殊な裏地や素材によって熱の出入りを遮断する構造になっています。
一般的なポリエステル製カーテンは、遮光性は高くても断熱性能が低く、冷気や熱気を通してしまいます。
一方で断熱カーテンは、冬場の暖房効率アップだけでなく、夏場の冷房費削減にも効果があります。
特に「断熱+遮熱+遮光」の三重機能を備えたカーテンは、日射熱を約40〜60%カットできるものもあります。
価格は通常のカーテンよりやや高めですが、エネルギーコスト削減を考えれば十分に見合った投資です。
カーテンレールの上部やサイドからの隙間をふさぐ「カーテンボックス」やマグネットも併用するとより効果的です。
⑤断熱カーテンの導入効果
断熱カーテンの導入によって、エアコンの稼働時間を短縮でき、最大で10〜15%の電気代節約につながるとされています。
特に西日が強く当たる窓や、直射日光を長時間受ける部屋では、その効果は大きくなります。
また、室内の温度ムラが改善され、エアコンの温度設定も1〜2度上げることが可能になります。
温度設定が1度上がるだけでも、約10%の冷房費がカットできるというデータがあります。
省エネ・快適性の両面から見て、断熱カーテンは費用対効果の高い選択肢と言えるでしょう。
設置も簡単で、賃貸物件でも導入しやすい点も評価できます。
⑥カーテンで間仕切りの検討
断熱目的での間仕切りカーテンの導入も、冷房効率を高めるうえで非常に有効な手段です。
特に広いリビングや、玄関とつながっている空間では、空調効率が悪くなりがちです。
間仕切りカーテンを使えば、冷房範囲を必要最小限に抑え、設定温度を高めに保っても快適な空間が得られます。
また、断熱だけでなく、プライバシー確保や生活動線の整理にも役立ちます。
100均やホームセンターで手軽に購入でき、設置も突っ張り棒を使えば工事不要です。
家族構成やライフスタイルに合わせて、柔軟に使える点も魅力ですね。
室外機カバーのタイプ別おすすめ3選
「用途や設置環境にあわせて選べる人気の室外機カバーを3タイプご紹介します。 どれもAmazon・楽天・Yahoo!ショッピングで比較できるので、ご自宅の状況に合うものを探してみてください。」 1.アルミパネルタイプ(定番・万能) おすすめポイント: 遮熱効果が高く、シンプルで設置しやすい 直射日光から室外機をしっかり守る


室外機カバーや節電グッズは100均だけでなく、人気ランキングも要チェック!本気で夏の電気代を下げたい方は通販で“室外機カバー”や“遮熱カーテン”を比較検討してみてください。
☀️ 電気代節約と快適さを両立したい方はこちらもチェック!
室外機カバー以外にも、遮熱カーテンや断熱カーテンを活用することで冷房効率をさらに高められます。
下記の記事では、コスパ・デザイン・機能性に優れた人気通販ショップを徹底比較しています。
安くて満足できるおすすめショップ カーテン通販で安くてコスパ最強おすすめ3選
一人暮らし・女性向けの選び方も徹底解説 遮光カーテン安いおすすめ通販3選
おしゃれで機能的な店舗を徹底比較
👆 気になるショップをタップしてチェックしてみてください。
まとめ|ダイソー 室外機カバー 電気代を正しく理解して節電を
ダイソーの室外機カバーは、手軽で安価な節電アイテムとして注目されていますが、取り付け方を誤ると逆効果になるリスクもあります。
実際の節電効果は5〜10%程度とされる一方で、放熱を妨げたりメーカー保証が無効になったりする可能性があるため、慎重な判断が必要です。
より確実な電気代削減を目指すなら、遮熱カーテンや断熱フィルム、間仕切りカーテンなど、室内側の断熱対策を中心に実施するのが効果的です。
快適な室内環境と節電を両立するには、複合的な対策の組み合わせが重要です。
以下のリンクも併せて参考にしてみてください。










